・古い本をブックオフに出すつもりで整理したときに遠藤周作の小説「沈黙」が出てきた。昭和44 年版だ。購入したことはすっかり忘れていた。 大学生の時だ。夏季休暇に高校の友人と6人でテントを担いで九州一周旅行をして「日本二十六聖人記念館」に立ち寄り、キリスト教弾圧や殉教を知り、もっと知りたいと思ったのだ。確か「沈黙」の情報も有ったので、帰宅後すぐに購入した。禁教令により、宣教師や信徒が捕らえられ拷問にかけられるが、どうして人間が人間に対してこのような惨いことが出来るのかと驚愕し、困惑した。多くの宣教師や信者がそれに耐え、甘んじて殉教して死んでいったことに更に驚いた。「転びバテレン」の情報を記念館で知ったとき、何故他の人は転んで棄教しないのか?転べばいいのに。命より大切な信仰が理解できなかったし、このようなことが有っていいのか?と思った。
著名な歴史家が「徳川実紀は200年ほど後に書かれたものなので信用しない。」とテレビで語っていた。また別の著名な歴史家の講演時に質問したことがあるが「大奥で不倫的?なことがやれる環境とは思えないし、秀吉の坂本城時代に側室が懐妊したとの記録があるので、やはり実母はお江と思う」と言われました。しかし、秀忠は嫉妬深いお江の目を盗んで大奥の女中に手を付けて後の会津藩主保科正之を産ませている。お江を憚かり子供は高遠藩に養子に出されていたが、将軍家光に弟と認知され、人柄も買われて会津藩主に抜擢された。坂本城時代の側室懐妊が本当に秀吉の子であったかどうかが定かではない。 家光誕生以前にお福が大奥に上がっていたという記録がある。謀反人明智光秀の重臣齋藤利光の娘お福の不幸に同情した家康の肝いりだったという説がある。天下人になれた一つの要因が明智光秀の謀反だったので、家康が同情したと推測する歴史家もいるようだ。将軍家の嫡男の乳母を公募すること、そして面接の時点で齋藤利光の娘と分かりながら乳母に採用したという話はどちらも不自然で到底信じられない。これは歴史家も認めているようだ。お江が家光の生母なら、何故徳川実紀でわざわざ事実を曲げる記述をしたというのだろうか?徳川家にとって不都合な話にする理由が見つからない。信用するかしないかではなく、歴史家はその意図をどのように解釈しているのだろうか?徳川実紀を作成した時点では徳川家や幕府内では周知のことでもあり、そろそろ時効だと思ったので事実を書き残したと解釈する方が納得し易い。家光が春日局を実母のように慕う一方、秀忠とお江を憎んでいるようないくつかの事例がある。また春日局の家光に対する異常ともいえる並外れた尽くし方は乳母の愛情をはるかに超えている。春日局が家光の生母と窺えるのではなかろうか?歴史家が史実、古文書、その行間をもっと読み解いて 我々素人に解説してくれるのを期待する。
・1674年、第2代水戸藩主・徳川光圀公が47歳のとき、養父母・お梶の方の墓所の鎌倉・英勝寺に墓参するため、水戸城から下総・上総・安房を経て鎌倉に出向いて、その後江戸小石川の水戸徳川邸に帰着しているが、この時の紀行文を「甲寅紀行」(こういんきこう)としてまとめている。そのうちの房総(千葉県)紀行の工程と宿泊場所を「甲寅紀行」や他の史資料により調べる。おおぜいの随行者(300人以上)を従えたご一行は、寺院、旅籠、庄屋の家、豪農の家に分宿したのだろうが、具体的な名前はわずか、光圀公が宿泊された酒々井の地蔵院と姉崎の妙経寺(みょうきょうじ)だけであった。それ以外は各宿泊地の伝承がどの程度残されているかによるが、現時点では承知していない。(2023年8月1日)
・大奥は3代将軍家光のときに春日局が家光の難色の悪癖があったために、世継ぎを心配して設置した。本丸御殿は表、中奥、大奥に分かれていて、大奥は1,000人以上の女の園で、且つ女の戦いの場でもあった。広さは2万平方メートル。「玉の輿」の語源になった家光の側室になった八百屋の娘・お玉、大奥御年寄・絵島の「絵島事件」、第11代将軍家斉の愛妾・お美代の方、公家出身の上臈年寄・姉が小路の活躍、第13代将軍家定の正室・篤姫、第14代将軍・家茂の正室・皇女和宮等数々のドラマの物語。
『おたけ騒動』とは、1695年上総国市原郡深城村で害獣の猪鹿を駆除中に山猟師が鉄砲で百姓の女房・おたけを鹿と間違えて殺してしまったことに始まる。関係する近隣の村の名主ら10人が伊豆大島と三宅島に遠島、ほかに9人が追放となり、そのうえに土地家屋没収という驚天動地の一大事件である。
この騒動に絡み、次郎兵衛の下僕・市兵衛が主人・次郎兵衛の赦免を願い出た。その献身的かつ並外れた赦免嘆願運動が幕閣を動かし、ついには11年後に次郎兵衛のみならず生存していた流人や追放者全員がご赦免となったという美談であり、空席となっていた姉崎村の総名主に推挙され、苗字帯刀まで許されたという出世譚である。(2023年12月6日)
・徳川斉昭と上臈年寄り・唐橋の密通事件で将軍継承問題(大奥の番外編)
・家斉の7女の峯姫が水戸8代藩主・斉脩(なりのぶ)に嫁ぎ、大奥の上臈年寄の唐橋を連れてきた。好色で有名な水戸斉昭が、唐橋と密通し、孕ませてしまった。このスキャンダルで、第14代将軍継承問題(一橋慶喜と慶福(のちの家茂))、更には日本の維新に大きく影響した可能性もある。
・新井白石と土屋鶴姫は直接の繋がりはない。しかし後に白石が将軍の侍講として幕政改革「正徳の冶」を主導するが、偶然とは言え、鶴姫が結果的にその機会を作ったともいえる。久留里藩第3代当主土屋頼直がその美貌で有名だった豆腐屋の女房・鶴に横恋慕し、夫を無実の罪で捕らえ、離縁させ、鶴姫と名を改めさせて城内に住まわせる。この狂気じみた行いを諫めるために家老・青木康太夫は切腹する。鶴姫が豆腐屋での冷たい水での豆腐つくりの苦労話を頼直にぼやいたところ、 それを聞いた頼直は十右衛門を捕らえ、首を刎ねてしまう。十右衛門の息子・十兵衛は仇打ちと称し、鶴姫の命をつけ狙うようになる。鶴姫は宝林寺に避難するが、十兵衛の偽の手紙におびき出され、城に向かうところを切られて絶命する。鶴姫に同行していた鶴姫の兄も背中を切られたが、生き延びて江戸城に訴え出る。この不始末を知った幕府により、狂気を理由に土屋家を改易し城も破却した。
・「おくのほそ道」のタイトルはよく聞いていたが、ほとんど知らない。有名な2~3句以外はほとんど知らなかったし、その意味はほとんど理解できていない。ある時、タイトルは忘れたが、テレビ番組で「松尾芭蕉は隠密だったか?」という内容の番組を見て、興味があったので、童門冬二の「異聞 おくのほそ道」を読んでみた。「芭蕉は隠密ではないが、同行した弟子の河合曾良はのちに隠密にかかわる仕事に就いているので、旅の間に隠密的な活動をしていたとしても不思議ではない。」と理解した。その場合、芭蕉が知っていたかどうかは分からないが、知っていたと解釈する方が分かり易い。それよりも、「芭蕉の終わらない旅」や「奥のほそ道」を少し調べてみることにした。芭蕉の旅は膨大なのでほんの概要だけにして、「おくのほそ道」を少し調べて、さわりだけでも理解したいと思った。 とても奥が深そうで、俳句に疎い自分にはとても神髄に触れられないと感じた。最初から分かっていたことではあるが。
天保水滸伝をはじめ江戸時代の任侠ものの映画を子供のころに良く見た。このところ、テレビドラマでめっきり見ない。皆無と言える。子供の頃見た映画の天保水滸伝のストーリーは?それにヒーローだった侠客の実像は?それに房総、特に下総に侠客が多いので不思議に思っていた。講演の資料を読み直して、調べてみて何となく理解できた。 悪政の相給制度(一村が複数の支配者に分割知行される、房総に多い)等により、農民が税の重みに苦しみ、そこから抜け出すために自然発生的に侠客が増えた。 ヒーローでも悪役でもなく、民衆が作り出す社会の一部としてのアウトローと分かる。尚、最近、この関連が映画やドラマに取り上げられないのは時代劇そのものが下火になっている上に、その中でも江戸の奉行や盗賊改めに比して田舎の捕物は地味だからかも知れない。

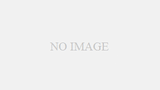
コメント